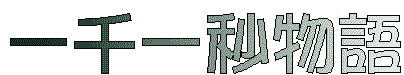
ゆうべ枕べにたれかがやってきてしきりに何やら云ったけれど何をいっているのかちっともわからないので黙っていたらそれはたいそう嘆いて帰って行ったがいま思い出してみるとどうやら昨夜の月夜にミルク色にかすんでいた空から降りてきたお月様らしかった
ある晩黒猫を捕まえて鋏でしっぽを切るとパチン!と黄色い煙になったしまった頭の上でキャッ!という声がした窓をあけると尾のないホーキ星が逃げて行くのが見えた
「一千一秒物語」は、こうした──というより、詩のような小説、小説のような詩とでも言うのでしょうか──をたくさん集めた作品集です。
その一編一編が、せいぜい数行のなかに閉じ込められたイメージの奔流です。
これといったストーリーがあるわけでもなく、こういうことがありましたというだけで、後はただ突き放してしまってそれでおしまいという、お話としてはただそれだけの物ばかりなので、これは紹介するのがとても難しい。
とにもかくにも現物に触れてみて、作者が提供する豊かなイメージを読みとってほしい作品です。
作者の感性の世界に飲まれてしまって、その特異な世界に浸り切ったときの快感は、どうにも捨てがたいものがあります。
「一千一秒物語」は、現在ならば、ショートショートというジャンルに分類されるものなのでしょう。
これが書かれたのは、そういう言葉もジャンルもまだなかった、1923年(大正12年)以前のことなのです。
「月から出た人」、「星をひろった話」、
「流星と格闘した話」、
「お月様とけんかした話」、「月光鬼語」、
「ポケットの中の月」、「月光密造者」、
「彗星(ほうきぼし)を獲りにいった話」、
「ガス燈とつかみ合いをした話」、
「自分を落としてしまった話」、
「星でパンをこしらえた話」、「星におそわれた話」、
「お月様をたべた話」……等々。
表題を見ているだけでも、なんだか不思議な気分になってきます。
読んでいて感じる不思議な懐かしさ、読後の不思議な余韻、奇妙な眩惑感(げんわくかん)、酩酊感(めいていかん)……。
作者の感性が言葉になると、世界はキラキラとした冷たい硬質の透明なガラスに変わります。
「一千秒物語」の他にも、『一千一秒物語』には、魅力的なお話がいくつか収録されています。
「チョコレット」は、まだ人々が起き出さない早朝の並木道でポンピイが出合った、妖精のロビン・グットフェローのお話です。
薄い緑色の羽をもち、五、六才の子供の大きさしかないロビン・グットフェローは、赤いとんがり帽子をかぶって、黄色と真紅色のズボンをつけ、ガラスの靴を履いて、ポンピイが本で読んだとおりの妖精の姿をしていました。
けれども、森のなかに住んでいて、朝方には帰ってしまうというロビン・グットフェローが、街なかをこんな時間に歩いているというのは、本で読んだお話とは違っています。
それに、妖精はもうとっくの昔に滅びてしまったはずなのに……。
人間に追われて、妖精ではやっていけなくなってしまったかれらは、今では彗星(ほうきぼし)をやっているのです。
そして、地球の近くを通ったときに、地上が懐かしくなってちょっと降りてみたというわけでした。
後半は、ポンピイのチョコレットのなかに入って出てこなくなってしまった妖精を何とかしようとするお話です。
ポンピイの出合ったロビン・グットフェローが本当は妖精なんだか彗星なんだか分からなくなってしまったり、彗星の目から見た天や地上の様子が夢幻的に描写されたりと、
これは「一千一秒物語」をちょっと長いお話にしてみたといった感じの、やっぱり、目眩(めく)るめく楽しく不思議なお話です。
「黄漠(こうばく)奇聞」──、これは、砂漠のまんなかに神々の都にも勝る壮麗な都を作り上げた王様のお話です。
蛮族の頭(かしら)から一夜にしてなり上がった王様は、神々の像を撃ち壊し、神を信じることなく、自分の力だけを信じて、神の存在しない、けれども、人々の住みやすい理想的な都を作ります。
なのにふと、砂漠育ちの粗野な自分に本当にこんな偉大なことを成す力があったのかと、彼は疑問を持つのです。
やはりどこかに神の力が働いていたのでは……と。
そうした疑問をもったとき、聡明な王の理性は狂います。
空にかかる月が自分の力の届かない神々の存在を証明するように思われて、彼は都に翻る自分の旗に月をはめ込もうと試みます。
月と同じ物を造るようにと命じられた学者たちには地獄の日々が待っていました。
いくら努力してもできるはずがありません。
王の期待を裏切った学者たちは次々に殺されていくのです。やがて王は、みずから、空にかかる月を取りに、兵を率いて砂漠に討って出るのですが……。
“神々の物語”の章でご紹介する『ペガーナの神がみ』の世界がほの見える、これは、神々と人間の虚無と幻想の物語です。
物語のなかに、“ペガナ”、“マアナ・ユウド・スウシャイ”、“ムング”、“ダンセイニ”といった、『ペガーナの神がみ』のなかの名前を拾い取ったときには、なんだかちょっと嬉しい気持ちになりました。