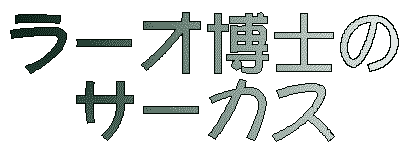
中国人ラーオ博士の率いるサーカスがアリゾナの田舎街アバローニ市にやって来た。
地方新聞アバローニ・モーニング・トリビューンに物凄く大げさな広告を載せて……。
薄汚い荷馬車三台きりのみすぼらしいサーカスである。
ところが、荷馬車を引いているのは、ユニコーンにスフィンクスに黄金のロバ。
手綱を取っているのは、サチュロスや古代ギリシア時代の哲学者であるティアナのアポロニオスなのだ。
神話や伝説の生き物たちを見せ物にしてやってきた、ラーオ博士のサーカスの不思議な一日の始まりであった。
アバローニ市の人々は、アメリカの片田舎に住む普通の人々である。
彼らは自分がどんな凄いものを見ているかということに気がつきもせず、ちょっと恐ろしくていかがわしい、そして、胸踊るイメージの、普通のサーカスを見るのと同じ感覚で、このサーカスを楽しんでしまう。
ラーオ博士もまた、このサーカスを普通のサーカスと同様に、珍しい動物や奇形の人間のテント、奇術、占い、成人男子だけが入場できるピープ・ショーといった見せ物に仕立てている。
ただ、そこで見られるのは、本物のキマイラ、人狼、人魚、サチュロス、オオウミヘビ、ロック鳥の卵、メデューサなのだ。
奇術と人々が思うのは、演者みずから主張するように、目眩(くら)ましではなくて本物の魔法であり、占い師は真実の未来をしか語らない。
ショーを演じて見せるのはファウヌスとニンフであった。
そして、本物の神話や伝説の生き物や本物の不思議と、ごく普通のアバローニの人々との間には、ちぐはぐな行き違いから、次々と滑稽な騒動が繰り広げられていく。
人狼が狼から人間に変わるのを見たラリーは、彼の期待したようにそれが美しく官能的な若い娘には変わらず、萎びたお婆さんに変わってしまったと文句を言う。
オオウミヘビと長々と大真面目な会話を交わしたトリビューン紙の校正員エティーオインは、ラーオ博士にインタビューしてきたと自慢するトリビューン紙の女性記者に、「ぼくなんぞ、いまウミヘビにインタビューしてきたところだぞ」。
家族と一緒に見物にきて、テントのなかの巨大な卵をコンクリートだと言い張るパパの前で、巨大なロック鳥の雛が孵るのを見てびっくりしたパパは、それでも何でもないふりをして、「さあみんな、あっちへ行こう」……。
こうした、滑稽なエピソードを積み重ねながら、物語は一万一千人の登場人物によって演じられる(?)、古都ウォルダカンにあるヨトル神の神殿で繰り広げられるいけにえの儀式のクライマックスへと雪崩れ込んでいくのだが、これがまたなんとも凄まじい代物だったのだ……。
 街の片隅に、ある日突然現れる、いかがわしい縁日の見せ物小屋……。
街の片隅に、ある日突然現れる、いかがわしい縁日の見せ物小屋……。
人は、本物の不思議を見られるかもしれないと、もしやの期待を抱いてそうしたところに出かけていくわけなのですが、ここに登場するアバローニ市の人々は、そうした期待が現実となった羨ましい人々です。
もっとも、彼らはそうした幸運をきちんと受け止めるにはあまりにも普通の人間でありすぎました。
本当は、ファンタジーファンの私たちの前にこそ、こうしたサーカスが現れてくれると嬉しいんですけどね。
『ラーオ博士のサーカス』に描かれるのは、大笑いと言った類の滑稽さではありません。
けれども現実に、現実の現代世界にファンタジーの生き物たちが生きていて、魔術が存在するのなら、やっぱり、こんなふうな体たらくになってしまyうかもしれないと、思わず納得してしまうおかしさが秀逸です。
あの素晴らしいファンタジーの生き物たちが、あんまり卑少になってしまって悲しい思いも否めませんけれど……。