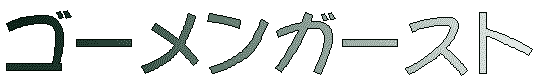
外壁の周囲に貧民たちのあばら屋をまとわりつかせて聳(そび)えたつ、重苦しい石の集合体ゴーメンガースト城。
増築に増築を重ねて奇怪な外観を呈し、巨大な石の迷路と化したこの城では、もはやその意味を知るものも絶えていなくなってしまった“掟”と“儀式”が日々を支配していた。
そしてそこでは、人間存在のカリカチュアのような奇怪で醜悪な住人たちが、それでもそれなりに、人間的な毎日を住み暮らしていたのである。
喜びと悲しみ、愛と憎悪、そして、嫉妬と陰湿な陰謀と……。
タイタス・グローンは、ゴーメンガーストの当主となるべくこの城に生を受け、父の死によって、わずか二才にしてゴーメンガースト城の第七十七代当主の座に着いた。
生まれたときから特別の人間であったタイタスは、常にまわりのものたちの監視の目にさらされて、自由な時間を持つということがなかった。
彼は“掟”と“儀式”に縛られた毎日から脱出して、特別ではない、ただの一人の人間になることを夢見ながら成長していく。
物語には、タイタスとは対象的に、まったく取るに足りない生まれの人間が登場して重要な役割を果たすことになる。
台所の下働きから、己の才覚だけを頼りにゴーメンガーストの城主にまで成り上がろうとするスティアパイクである。
タイタスの父であるセパルクレイヴが狂ったあげくに死んでしまったのも、スティアパイクの陰謀のためだった。
多くの人間が彼の毒牙の犠牲となり、やがて、その魔手はグローン伯爵家そのものにまで及ぼうとする。
そして、城を襲う大自然の猛威……。
さまざまのものを失いながら、ゴーメンガーストの危機にあたって大活躍したタイタス。
だが彼は、城の生活がもとの日常に戻ったとき、ゴーメンガーストを捨てて外の世界へ出奔する。
しかし、外の世界でタイタスを待ち受けていたのは、ゴーメンガースト城よりも、さらに奇怪で異様な世界であった……。
外面も内面も奇怪な、膨大な数の登場人物たち。
彼らの織りなす醜怪なゴーメンガースト城の毎日は、理解できないおとなの世界に放り込まれた、感じやすい心を持ったこどもが見る悪夢の世界です。
時間という癒しの手が嫌なことを忘れさせてくれ、また、現在おとなであることを厭(いと)う人々がこども時代を美化して喧伝(けんでん)しているために、私たちはつい、こども時代が懐かしい夢の世界であったように思いなしています。
けれどもこども時代の思い出は、決して素晴らしいものばかりではありません。
実際は、思い出したくない嫌なこともまた、楽しい思い出と同じ数ほどあるはずです。
こどもであれおとなであれ、結局、今現在直面している現実は、辛いことの多い、あまり楽しくない世界なのかもしれません。
《ゴーメンガースト》は、そのこども時代の悪夢からの脱出を描いたとも考えられる物語なのです。
けれども、こども時代の悪夢から脱出した後(あと)も、やはり世界は悪意と謎に満ちた奇怪なものであることに変わりはありません。
私たちの生きている世界そのものが、必ずしも割り切れる、理解しやすいものではないのですから。
産業革命以後のテクノロジーを持たないゴーメンガーストを脱出したタイタスの前には、私たちの世界と同様のテクノロジーを持った、一見して、私たちの世界かとも思われる現代的な風景が現われます。
自動車、飛行艇、工場、警官、裁判に判事……。
重苦しい悪夢のような異質な世界を後にして、ようやく馴染み深い世界が舞台にになり、やっと一息つけると思いきや、実は、この世界はゴーメンガーストよりももっと異質で異様な世界だったのです。
少なくとも、ゴーメンガーストの人間たちは人間の感情を持ち、彼らの行動原理も考え方も非常にわかりやすいものでした。
けれどもここには、人間的な感情を持たない謎のものたちがいて、世界は誰にも把握することのできない原理原則のもとに動いているのです。
この世界ではゴーメンガーストのことなど誰も知らず、みずからの存在を証明するものを何も持たないタイタスは、浮浪者として裁かれるしかありません。
そして彼をつけまわす、兜(かぶと)を被(かぶ)った、正体のわからない奇怪な二人の男たち。
タイタスは、振り捨ててきたはずのゴーメンガーストが無性に懐かしく、そこに帰りたいと切望します。
けれども、この世界でさまざまに翻弄されて、自分の居場所すら定かにわからなくなってしまったタイタスには、誰も知らないゴーメンガーストに帰る術(すべ)がありません。
タイタスはゴーメンガーストの存在も、自分の正気すらも疑い始めます。
主人公のタイタスやほかの何人かを除いて、この物語の大勢の登場人物たちは皆、奇怪で醜悪で極めて強烈な個性の持ち主ばかりです。
かれらの面ざしや心の動きは、膨大な量のさまざまなエピソードによって非常に精緻に、そして自然に描かれます。
そのためなのでしょう
《ゴーメンガースト》は、私にとって、最初はちょっと読みにくい物語だったのですが、読み進むうちに、これら醜怪な登場人物たちの心の動きに引き込まれ、いつの間にか、お気に入りのキャラクターを応援している自分に気がつきました。
登場人物たちを本気で愛したり憎んだりしてしまっていたのです。
そうなってしまったらもう、彼らの運命が気になって気になって、ページを繰るのももどかしいというものです。
というわけで、この物語には、たくさんの贔屓(ひいき)の登場人物ができたのですが、なかでも私のお気に入りは、タイタスの母であるガートルードです。
彼女は偉大な身体と偉大な心を持って異彩を放つ、恐るべき伯爵姫です。
彼女の愛情や才覚は猫と鳥とに向けられて、滅多に人間に向けられることはありません。
けれども彼女は、真に自分が必要とされるとき、タイタスやゴーメンガーストを守って雄々しく立ち上がります。
「総てがタイタスに集中している。石も山も──〈血〉も〈儀式踏襲〉も。あの子に手出しをしてみやれ。傷つけられた髪のひとすじにつき、心臓を一つ停めてやるわえ。騒ぎが収まったあと、わたしに慈悲の心があれば──それだけで済む。無ければ──さてどうしてくれようねえ?」
というわけで、彼女は凄まじい女丈夫です。
こういう、頼もしくて雄々しい(という言葉は本当は女性に使うのはおかしいわけで、これもやっぱり女性差別だ!!)女性を見ていると、非常に爽快な心地がします。
彼女が美人ではなく、けれども、そんなことをまったく気にすることなく、自分自身として堂々と生きているところも素敵です。
《ゴーメンガースト》は、『タイタス・グローン』、
『ゴーメンガースト』、『タイタス・アローン』の三部をもって終わってしまっていますが、これは作者の死によってこうなったもので、作者の構想としては、この物語はまだまだ続くはずのものだったようです。
確かにこの三部作のおしまいには、非常に感動的なある種の結末が呈示されますが、作者がこの先物語をどこへ持っていこうとしていたか、タイタスが今度はどこへ行こうとしていたものか、でき得ることなら読んでみたいと残念でたまりません。
なお、非常に分厚で内容も重く、細部の描写の詳細なこの物語、始めからきちんと読み進むのはちょっときついかもしれません。
私は、まず、外伝とも言える「闇の中の少年」を読み、それから、
『ゴーメンガースト』、『タイタス・アローン』と読み進み、第1巻の
『タイタス・グローン』を一番最後に読むという、非常に邪道な読み方をしてしまいました。
決して取りつきやすい物語ではありませんが、引き込まれてしまったらちょっと離れられない、強烈な印象の物語です。