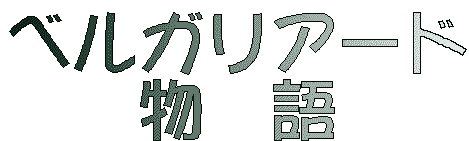
ガリオンはファルドー農園の平和な台所で、料理女のポルおばさんに育てられていた。
彼の右の手のひらには生まれつき丸くて白い印があり、黒い馬に乗った黒ずくめの不気味な男が幼いときから彼を監視しているようだった。
しかし彼の人生は農園の使用人のほかのこどもたちと変わりなく、思春期を迎えたガリオンは、農園一の美少女で、小悪魔的に少年たちを弄(もてあそ)ぶズブレットへの恋に悩んでいた。
ところが、ガリオンのこの平和で平凡な生活は、ある日突然終わってしまった。
ポルおばさんの昔からの知り合い、謎の語り部ウルフ老人が二度目にファルドー農園を訪れたとき、ポルおばさんはウルフとともに、ガリオンを連れて旅に出ることになったのだ。
ガリオンにはわからない、何か重大な用事ができたらしい。
ポルおばさんを愛している鍛冶屋のダーニクが、彼女を守るため、ついてくることになる。
こうしてガリオンの波乱万丈の冒険の旅は始まった。
実はウルフ老人は、ほとんどこの世界の始めから、七千年もの永きにわたって生きている伝説の大魔術師ベルガラスその人だったのだ。
ポルおばさんはベルガラスの娘で、やはり大魔術師のポルガラだった。
そしてガリオン自身、大魔術師の素質を持つ、リヴァ王の直系の子孫であることを知らされるのである。
ポルガラは、世界制覇を企む邪神トラクの勢力にガリオンのことを知られるのを恐れ、ファルドー農園に隠れて密かに彼を育てていたのである。
ガリオンは、邪神トラクに対する最後の切り札ともいうべき存在だったのだ。
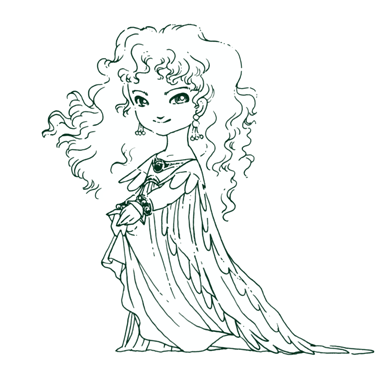 お話の基調は完全にシリアスなものですが、全編にあふれるユーモア感覚がとても楽しい大長編ファンタジーです。
お話の基調は完全にシリアスなものですが、全編にあふれるユーモア感覚がとても楽しい大長編ファンタジーです。
例えば……。
ガリオンは魔力を使うのを嫌がって、随分長い間魔術師の訓練を受けるのを避けていたのですが、とうとう諦めて練習を始めます。
訓練で巨大な石を動かすようベルガラスに言われたガリオンは、「押せ」と一言自分の魔力に命じて、首尾良く石を動かすことに成功します。
けれども、ベルガラスはおかんむり。
「わしは押すように言っただけだ。“押せ”と言えとは言わなかったぞ」
「でも、ちゃんと転がったじゃない。言葉の使い方が違うと何かあるわけ?」
「スタイルの問題だ」老人は感情を害したようだった。「“押せ”というのは──ちょっと幼稚すぎる」
ガリオンは力なく笑った。
「なあガリオン、やはり我々は絶えず威厳を保つようにせんとな」老人は気取って言った。
「もしわれわれが“押せ”とか“倒れろ”というような言葉しか使わなかったら、誰も敬意なんか払ってくれなくなるぞ」
ベルガラスはたいていのファンタジーに出てくる近寄りがたく厳(いかめ)しい魔法使いとは違って、気さくで親しみやすいお爺さんなのですが、魔法使いらしさを演出するために、こんな苦労をしているのですね。
もしかしたら、ほかのファンタジーの厳(おごそ)かな魔法使いたちも、実は同じ苦労をしているのかもしれません。
ベルガラスとポルガラの、愛情に裏打ちされたかけ合い漫才は秀逸です。
この物語には、その身分にふさわしく自分を保つため、こうした涙ぐましくも滑稽な努力をしている人間がたくさん登場します。
作者の人間観察の確かさと余裕なのでしょう。
鮮やかに描き分けられた登場人物は、それぞれみんな、とても自然で魅力的です。
ポルおばさんことポルガラは、どこの王室へ顔を出しても恐れ敬われる存在で、そういう場所での彼女は非常に威厳のある申し分のないレディの顔をしています。
けれども彼女は、台所に立って誰かのために料理を作っているときが一番幸せそうです。
彼らの道連れで、随分力になってくれる、“詐欺師”兼“軽業師”兼“泥棒”兼“スパイ”のシルクは、実はドラスニアの皇太子です。
けれども彼にとっては、王宮の外にあって詐欺師をしているときのほうがその本来の顔であるらしく、必要のないときでも思わず詐欺師稼業に励もうとしてしまいます。
一緒に旅をするバラクやヘターも、高貴な出自を持ちながら、それぞれの必要から庶民のなかに立ち混じって生活し、その暮らしを彼ら本来の窮屈な生活よりも楽しんでいます。
たくさんの危難を経た後(のち)に、彼らにはハッピーエンドの大団円──ならぬ大縁談の結末が待っています。
この最後の最後の場面にも思わず笑ってしまうエピソードが用意されていて、読後感をいっそう幸福なものにしてくれます。
随分長い小説ですが、読みやすいお話なので、読み始めるのに躊躇(ちゅうちょ)する必要はありません。
続編の『マロリオン物語』──これも大長編です──も刊行されていて、さらなるガリオンの冒険の旅が大いに読者を楽しませてくれます。