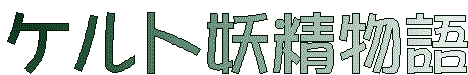
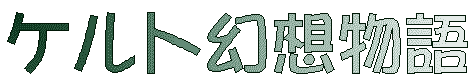
タイグ・オケインは、金持ちの家の手に負えない道楽息子だった。
彼はある真夜中、家へ帰ろうと道を歩いていて、向こうから何か重そうなものを運んでくる大勢の妖精たちと出会ってしまう。
妖精たちは、タイグ・オケインを取り囲み、運んでいたものを投げ出した。
なんとそれは気味の悪い死体だったのだ。
タイグ・オケインは、彼らからこの死体を押しつけられてしまった。
背中に負わされた死体は、タイグ・オケインにしがみついて離れない。
彼は死体の指示するとおり、死体を埋葬する場所が見つかるまで墓地から墓地へと歩き続けなければならないのだ。
朝までに死体を埋めることができないと、タイグ・オケインの命はないと妖精たちは言うのである。
ところが、教会の敷石の下を掘ってみれば、ほかの死体が出てきてそれが立ち上がり、恐ろしい声で彼を追い払う。
古い墓地では、何百という幽霊が、彼が墓地に入るのを妨害する。
はたして、タイグ・オケインは死体を無事に埋めることができるのだろうか……。
海の妖精メロウの一人クーマラ爺さんと仲良くなったジャック・ドハティ。
彼は、クーマラ爺さんが貸してくれた、海のなかでも息ができる帽子を被(かぶ)って海の底のメロウの住み家へ行って、一緒に楽しく酒盛りをした。
このときジャックは、クーマラ爺さんが海で死んだ人々の魂を集めているのを知り、知恵を絞って何とかこれを逃がしてやろうとするのである。
ジャックの奥さんまでも巻き込んで、この企てはどうにか成功する。
そして、魂を閉じ込めておくということになんの悪意も持っていなかったクーマラ爺さんは、ジャックが魂を逃がしてしまった後(あと)でも、なんのこだわりもなくジャックと仲良くつき合い続けたのである。
楽しい日々が続いたが、ある日を境に、クーマラ爺さんはふっつり姿を見せなくなってしまった。
何百年もの昔から生きてきたらしいクーマラ爺さんは、とうとう死んでしまったのだろうか。
それとも、どこか別のところへいってしまったのだろうか……。
 『ケルト妖精物語』と『ケルト幻想物語』の二冊の本は、十九世紀の終わり頃、当時まだアイルランドの地で信じられていた妖精やその他の不思議な物語を、アイルランド出身の詩人イエイツが採集し、分類して出版したものです。
『ケルト妖精物語』と『ケルト幻想物語』の二冊の本は、十九世紀の終わり頃、当時まだアイルランドの地で信じられていた妖精やその他の不思議な物語を、アイルランド出身の詩人イエイツが採集し、分類して出版したものです。
アイルランドに残されていたケルトの伝承のさまざまなお話、そして、イエイツによって書かれた各章ごとの解説や、付録の妖精の分類が、ケルトの民間伝承の世界を知る上で大きな助けになってくれる、たいへん便利でおもしろい本です。
アイルランド人によって実際に信じられ恐れられていた妖精は、「救われるほど良くもないが、救われぬほど悪くもない堕天使」、あるいは、「もはや崇拝もされず、供物も捧げられなくなってしまって、人々の頭のなかで次第に小さくなってしまった太古の土着の神々」と考えられていたようです。
こうしたケルトの妖精たちは、私たちが普通妖精に感じるかわいらしく愛らしいというイメージとは程遠く、もっと恐ろしい、ほとんど日本の妖怪変化のようなものだと思われます。
妖精は、ときに、気に入った人には福を授けてもくれるのですが、害を成すことのほうが多く、気紛れな妖精たちを怒らせることを恐れて、人間はなんとか彼らのご機嫌を取り結ぼうとします。
彼らのことを“グッド・ピープル”と呼び、敷居のところにミルクを置いてやったり、彼らの話を言いふらすことをはばかったりするのはそのためでした。
「触らぬ神にたたりなし」と敬して遠ざけられている日本の神様たちとも、なんとなく共通点があるようです。
妖精のお話のほかにも、この二冊の本には、魔女や幽霊、巨人たちのお話などがたくさん収められています。
ここで語られている巨人たちは、英雄たちの成れの果ての姿です。
妖精とは反対に、ケルトの伝説の英雄たちは語り継がれるうちに巨大になっていき、おまけに彼らは巨人の特性としての間抜けさかげんまで身につけてしまいました。
妖精のご機嫌を損じて、仕返しされた話。
妖精と仲良くつき合って、けれども、最後は悲しい別れをしなければならない話。
夜のうちに家の仕事を片づけてくれていた妖精に、お礼としてプレゼントをしたところ、喜んでいなくなってしまった話。
魔法にかかったプディングが踊りだし、おまけにそれを食べた人まで踊り出す、ドタバタ・コメディのような話。
お話とは言えないような、妖精の実見談──。
「十二羽の鵞鳥」「怠け者の美しい娘とその叔母たち」のように、グリムなどがヨーロッパの他の地で採集したものと同様のお話もあります。
楽しい話、恐ろしい話、また、心にじんとくるような話と、いろいろなタイプの話が揃っていますが、なんとも知れないもの悲しさが全編に漂っています。
それは、かつて偉大であった彼らの神々や英雄たちに対する、アイルランドの人々の哀惜の情のゆえかもしれません。