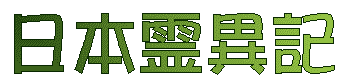

今は昔、あるところに猟師の兄弟がいた。
その日兄弟は、“待ち”という猟をしていた。
これは、木のまたに横様に木を結んだ上に登って、その下を鹿が通りかかるのを待つ猟の方法である。
9月の下旬の闇の深い夜で、物は見えず、兄弟はただ音だけを頼りに鹿を待っていた。
そのうちに、兄のいた木の上から手をさし下ろして、その髻(もとどり)を取って引き上げようとするものがある。
髻を掴んだものを探ると、痩せさらばえた人の手である。
鬼が自分を取って食おうとしているのだと悟った兄は、向かいの木に登っている弟に告げ、声を頼りに弓で射てもらう。
矢が当って、その化け者の腕が根本から射切られて、髻を掴んだまま残された。
その日、兄弟が家に帰ると、母のうめき声が聞こえる。
「どうしたのです?」と聞いても返事がない。
灯りをつけて、持って帰った化けものの腕をよく見ると、それは紛れもなく母の腕である。
そこで、兄弟が母の部屋の引き戸を開けると、母は起き上がり、彼らに飛びかかってこようとする。
兄弟は、「これは、あなたの御手か」と言って腕を投げ入れ、戸を締めて逃げた。
母は、その後いくばくもなく死んでしまった。
兄弟が近寄ってみると、母の片手はつけねのところからなくなっていた。
今は昔、小野の篁(たかむら)という人がいた。
彼が学生であった頃、事件を起こして罪を問われることがあった。
そのとき、西三条の大臣良相という人が篁のためにいろいろ働いてくれので、篁は彼に感謝していた。
年を経て篁は宰相になり、良相も大臣になった。
ところがあるとき、良相は重い病にかかって死んでしまった。
彼は閻魔王の使いに捕えられ、閻魔王宮に連れていかれて罪を定められることになったのだが、閻魔王の冥官の居並ぶなかに、なんと小野篁が混じっているではないか。
良相が不思議に思っていると、篁は閻魔王に良相の命乞いをしてくれる。
そのおかげで彼は生き返り、病も直ったのである。
その後、良相は篁と二人きりで話すことがあり、冥府でのことを聞いてみたところ、篁は少し微笑んでこう言った。
「先年のご恩をお返ししたのです。でも、これはまだ人の知らないことなので、誰にも言ってはいけませんよ」
称徳天皇の時代、紀伊の国熊野の村に、永興禅師(えいごうぜんじ)という、菩薩とまで称えられる徳の高いお坊さんがあった。
この永興禅師の元へ、ある日一人の禅師が尋ねてきた。
常に法華経大乗(お経の一つ)を称え、一年余りを永興禅師のもとで過ごした後、その禅師は山に入って修行をするため永興禅師のもとを去る。
二年ほどして、熊野の村の人は、山のなかで法華経を唱える声が幾日も幾月も止むことなく聞こえるので、尊くも不思議に思うようになる。
捧げ物をもって訪ねていっても、誰の姿も見えないのだ。
永興禅師がそれを聞いて山のなかへ訪ねていってみると、修行中に死んだのであろうあの禅師の屍があった。
さらに三年。経を詠む声はまだ続いている。
再び永興禅師が訪ねていくと、禅師の髑髏のなかにその舌がまだ朽ちずに新鮮なまま残っていて、経をとなえ続けていたのであった。
聖武天皇の時代、大和の国菴知(おうち)の村に大変豊かな家があった。
その家に、名を萬(よろず)の子という非常に美しい娘がいた。
家柄のいい人が申し込んでも拒み続けて、まだ誰とも契っていなかったのを、ある人が、美しい色に染めた絹を車三つに積んだたいそうな贈り物を持って、結婚を申し込んできた。
そこで嬉しく思って結婚を承知したのだが、その夜、寝所の内から「痛きかな」という声が三度聞こえた。
父母は慣れていないからだろうと思い、そのまま寝ていた。
次の日二人がなかなか起きてこないため、母が戸を叩いて呼んでみたのだが返事がない。
不思議に思って戸を開けてみると、娘は頭と一本の指を残して皆食われてしまっていたのである。
美しい色に染めた絹は獣の骨と変わり、車は茱萸(ぐみ)の木に変わってしまっていた。
『日本霊異記』は、九世紀、奈良時代に書かれた日本最古の仏教説話集です。
さまざまな因果応報譚を中心に、仏教の教化に役立てるべくたくさんのお話が集められているのですが、「奇異(めづら)しきことを注(しる)して……」とあるように、多くの不思議を集めたファンタジーの宝庫のような本となっています。
同じように、やはり説話を集めた『今昔物語集』は、十二世紀の平安時代に成立したものです。
これは、インド、中国、日本にわたっての千二百を越える莫大な数のお話を集めた分厚な本で、やはり不思議の物語が多数収められています。
共通の目的を持つためなのでしょう。『今昔物語集』には『日本霊異記』からの再話がたくさん見られます。
因果応報譚を多く集めたということで、後(のち)の世の怪談話にも通じる、というか、この考え方がもととなって「うらめしや」と化けて出てくる後(のち)の世の怪談話が生まれてくるわけですが、ここには近世の怪談のような陰惨な感じはあまりありません。
生き生きと描写された民衆の力強い生きざまは、陰惨や陰湿を寄せつけないしたたかなパワーを持っているのです。
それは当時の民衆が、江戸時代のように、まだ完全にはお上(かみ)の支配する秩序のなかに囲い込まれてしまっていないためかもしれません。
このため、淡々とした語り口で描かれたお話の数々は、仏教説話集という言葉から連想される説教臭さもあまりなく、たいへん興味深く読むことのできる楽しいものになっています。