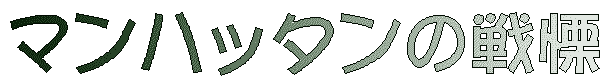
198×年8月のマッハッタン──。
始末屋ジャックは、その日、仕事の依頼を二つ引き受けた。
一つは、かつての恋人だったジーアからの依頼である。
これは、彼女の別れた夫の叔母グレイスの不思議な失踪を調査する仕事。
もう一つは、国連のインド代表団の一人、隻腕(せきわん)のクサムからの依頼だった。
辻強盗に襲われて瀕死の重傷を負ったインド人の老婆が盗まれた首飾りを、その夜のうちに見つけ出してほしいというものである。
クサムはひどく切迫した面持ちだった。
折しも、町からは浮浪者たちが急激に姿を消しつつあった。
社会保障番号も持たず、税金も支払わず、法律的にはまったく存在しないも同然の立場にその身を置くジャックの仕事は、非合法な手段をもって人々の面倒を解決する仕事──ときには、殺人までも引き受ける危険な仕事である。
ジーアと別れたのも、彼女がジャックの仕事を知ったためだった。
ジーアはジャックを人殺しと恐れ、彼との仲を解消してしまったのだ。
ジャックは首尾よく辻強盗を捕えて首飾りを取り戻すことに成功し、クサムから多大な謝礼をせしめた。
しかしその夜、ジャックによって両手を折られ、老婆と同じ病院に入院していた辻強盗は惨殺され、老婆はクサムの手によって病院から連れ出されて行方不明になってしまう。
一方、失踪したグレイスの捜査は、彼女の部屋にあった奇妙な液体にインド産の薬草の一種が入っていたことがわかっただけで、何の進展もない。
イギリスにいるジーアの別れた夫から、グレアムの妹ネリーに送られてきたチョコレート。
ジーアに対する思いを満たされないジャックの心の隙間に入り込むように、ジャックと急速に親しくなっていく、クサムの妹コラバティ。
彼女との情交の最中に現れた、不気味な黄色の二組の目。
クサムとコラバティの兄妹が肌身離さずつけている不思議なトパーズのネックレス。
クサムの船にうごめく不気味な黒い怪物“ラコシ”とは?
1857年にインドの寺院で起こった虐殺事件と、現代のマッハッタンで起こっている不思議な失踪事件の接点は?
やがてネリーまでが失踪し、ジーアの七才の娘ヴィッキーにも恐るべき復讐者の魔の手が迫る。
愛するものを守るため、裏の世界の仕事で身につけたすべてを使い、ジャックの命をかけた戦いが始まるのだった。
ハードボイルドとオカルトホラーを巧みに組み合わせて、現代の雑然としたニューヨークを背景に、息をもつかせぬサスペンスが展開します。
この手のタフな男の活躍する探偵小説の好きな読者には応えられない一冊です。
なんといっても、主人公であるジャックの造形が魅力的。
確かに彼の仕事は、法治国家のなかにぬくぬくと生きている人間にとっては恐るべき犯罪行為に違いありません。
けれど、彼の信念ややっていることには、ついつい納得してしまう正統性があるのです。
もちろん彼はそんなことを大声で言いはしないし、父親に対しては、苦労してきちんと表の世界で生きているふりもしています。
けれども、彼の信念と正義感は、裏の世界の仕事をしているために愛するジーアに糾弾されても、彼にそれ以外の生き方を許しません
彼がどうしてこういう仕事をするようになったかを明かすエピソードは泣かせます。
やむにやまれぬ憎しみにかられて法外の世界への一歩を踏み出してしまってから、彼にはこれ以外の生き方は有り得ないものとなってしまったのです。
そして、表の世界の力によっては解決できない事件にまきこまれてしまつたジーアが頼るのは、結局ジャック以外にはありませんでした。
ジャックをはじめ、登場人物の人物設定がたいへんしっかりした納得のできるものとなっていて、そういう意味でもとても読みやすい小説です。
恐ろしい怪物を操るインド人クサムも、必ずしも悪人としてではなく、彼の動機も感情も納得できるものに設定され、きちんと、それなりに立派な人物として描かれていて、気持がいいのです。
彼の信念は、かなり自分勝手で独りよがりで偏見に満ちたものですが……。
もっとも、そう見てしまうのは、こちらがインドの宗教の幾分かを知識として持っていて、また、アメリカ人とは違って、近代化が必ずしも錦(にしき)の御旗(みはた)ではないと思っている日本人であるがゆえかもしれません。
これを読んだ白人読者は、訳のわからない宗教を信じている、不気味で得体の知れないインド人に対する恐れを胸に抱いて、彼らに対する反発を胸に抱くことになるかもしれません。
著者みずから、かつての黄禍(こうか)論を扱ったスリラー小説群に影響を受けていると書いているように、やはりこれは、そう言った類(たぐい)のものを助長する危険な小説かもしれないという気もします。
まともな感情と理性の持ち主に見えたクサムの妹コラバティすら、最後の場面では、独りよがりの不気味な側面を見せるのです。
インドやヒンドゥ教の解釈にも納得できないものは残ります。
あるいは故意にこれをねじ曲げたものかもしれませんけれど……。
この作者の『城塞(ザ・キープ)』という小説は、吸血鬼とナチスという西欧小説の二大悪役スターを組み合わせて、これもおすすめのホラー小説です。
悪役の怪物に徹した吸血鬼が、不気味でたいそう魅力的。
“黄禍(こうか)”=“イエロー・ペリル”というのは日清戦争以後盛んに唱えられた論で、欧米人が恐れた、黄色人種の台頭が白人社会にもたらす禍いのことです。