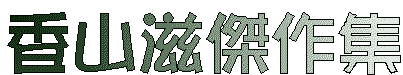
小田切史郎は狂気のなかに生きている。
彼と梨江夫人は、動乱のキューバで革命運動の巻き添えを食ったのだ。
スパイ容疑で拷問された上、愛娘のユリを目の前で惨たらしく殺されて、小田切史郎は狂ってしまったのである。
日本へ帰った梨江夫人は、交通の便の悪い武尊(ほたか)山麓の館に居を構え、夫妻は世間を捨てた逃避の生活を送っている。
狂気の夫の思うがままに振る舞わせ、愛情をもって見守ってやる。
それが梨江夫人の人生となっていた。
そんなある日、少女が一人、新聞の広告を見て働きたいとやってきた。
彼女の名はキキモラ。
髪を無造作なひっつめに結んで、額の狭い、バランスの取れない、それでいてひどく蠱惑的(こわくてき)な、まるでペルシャ猫のような顔立ちの娘である。
人を食ったかわいさのキキモラは、まめまめしくよく働いて、小田切史郎の狂気にも逆らわず、その妄想に調子を合わせて奉仕してくれる。
館は明るさを増し、部屋部屋は掃除も行き届くようになった。
そうして一緒に暮らすうち、梨江夫人は、キキモラを養女にしたいと思う程気に入ってしまう。
しかし、快活で純真と見えたキキモラは、幸福な人々を妬(ねた)み、その幸福を破壊するために忍び込む恐ろしい妖精だった。
人間の姿を装ってはいるが、実際は、岩と岩とのすきまに生まれ、魔法使いに育てられた小さな妖精なのである。
梨江夫人の相談を受けた宣教師のA・チャムレー師もまた、キキモラに幸福を奪われた犠牲者の一人であった。
小田切史郎が正気を取り戻すことが夫妻の不幸と思い込んでうろたえる梨江夫人を、チャムレー師は、安易な逃避のなかに逃げ込んだ、とんでもないエゴイストだと言って叱る。
ごまかしの生活は幸福とは言えないと気づいた梨江夫人に、チャムレー師は、キキモラを利用することを教えるのだが……。
「キキモラ」は香山滋の作品としては珍しく、ユーモアのある軽妙な味わいの小説で、登場人物たちそれぞれの温かい優しさが心地好い思いを残してくれます。
読み終えて振り返って見ると、「してやられた妖精」というサブタイトルも利いています。
香山滋には、不思議な魅力に満ちたたくさんの作品がありますが、そのほとんどは、重く、グロテスクな怪奇趣味にあふれる作品です。
生存本能によって獲得した不思議な力を有する、現代に生きる北京原人の末裔(まつえい)たちの物語。
東北に代々続く豪農の屋敷の広大な地下空間に、奇怪な儀式を繰り広げる、弾圧された宗教教団の物語。
伝説のソロモンの秘宝を求めて、インド最北の砂漠ダンガ・デザートに繰り広げられる愛憎劇。
報告者が、学会で発表の途中、一瞬のうちにミイラ化して死ぬという猟奇的な導入部から始まる、新種の人類オラン・ペンデクの物語。
幼女の時代を山猫(リンクス)に育てられたため、人と山猫(リンクス)の間で揺れ動く怪しくも美しいザーラと、彼女を巡る男たちの葛藤を描く物語。
落ちぶれ果てた見世物業者のもとに預けられた美しい腹話術師の少女にまつわる悲しい秘密の物語。
ゴビの砂漠の原始の森から、モンゴールの遊牧民の手ではるばる日本へ届けられ、美しい人間の女と化して主人公を誘惑する単眼の蝶の物語。
強烈な自我を備えたエロティシズムにあふれる女たち。
異国趣味にあふれた猟奇的な物語の数々。
怪しく危険に満ちた異空間。
原始への憧れ。
文明社会に侵略され、滅ぼされていくものたちへの哀惜の思い……。
さまざまな形で原始に触れた人間たちは、文明を離れ、原始の世界に身を投じます。
そして、これら香山滋のロストワールドは、コナン・ドイルのそれのように恐竜の闊歩する恐ろしい世界ではありません。
そこは、羊歯(しだ)植物とぬるぬるとした両生類の、暖かくじめついた母の胎内のような世界なのです。
明治生まれの作者が、昭和20年、30年代を中心として書いた作品群ということで、現代から見れば、思い違いや誤った知識なども散見するのですが、それすらもエキゾチックな不思議な異界の魅力と転化して、読者を眩惑(げんわく)して放しません。
いわば、禁断の果実の味とでもいうものでしょうか。
覗いてみてはいけなかったのではないかと、つい、まわりを見まわしてしまういかがわしさこそが、香山滋の作品の大きな魅力となっているのです。
すべての価値観が崩れて、だからこそ、すべての束縛がなくなって、空虚と解放感の奇妙に混在する戦後すぐの混乱した時代。
生存すらも困難であるほどに貧しくありながら、がむしゃらな明日への活気に満ちあふれたその時代──。
香山滋の小説を読んでいると、なんとなく、そんな時代の匂いが行間から漂い出してくるような気がします。
香山滋の、境界線を超越した、なんとなくいかがわしい小説が喜んで受け入れられたのも、そうした時代のエネルギーのためかもしれません。