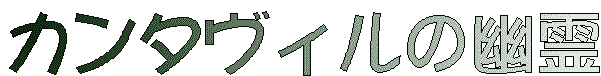
イギリスの幽霊屋敷、カンタヴィル猟園を買い取ったアメリカ公使の一家と、家つきの幽霊サイモン・カンタヴィル卿の、ユーモア溢れる、そして心温まる物語です。
最初にオーティス一家の前に現れた幽霊は、手錠と足かせの鎖の音を不気味に響かせて、青白い月の光のなか、ぼろをまとった異様な形相の老人の姿をしていました。
それまでは、話を聞いていただけで幽霊の存在を信じていなかったオーティス一家も、目の前に幽霊を見てしまっては疑いなど吹き飛んでしまいます。
もっとも、確かに幽霊の存在を信じはしたのですが、彼らはこれをちっとも恐がりません。
オーティス氏は“タマニー日の出印潤滑油”の小瓶を差し出して幽霊にすすめます。
それで、うるさい鎖の音を消して欲しいというわけです。
憤激のあまり、その瓶を力任せに床に叩きつけて廊下を去っていこうとする幽霊に、今度は双子たちの手で白い枕が投げつけられました。
びっくりした幽霊は、四次元の空間を利用して、ほうほうの体(てい)で消え去る始末となってしまいます。
それは、三百年もの長きにわたって数々の恐ろしい伝説を作り出してきた、誇り高いカンタヴィルの幽霊には、あまりに屈辱的な出来事で、彼は堅く復讐を決意するのですが……。
 アメリカ的合理主義−−十九世紀のアイルランド系イギリス人、ワイルドの描くアメリカですが−−と超自然的存在である幽霊との対決。
アメリカ的合理主義−−十九世紀のアイルランド系イギリス人、ワイルドの描くアメリカですが−−と超自然的存在である幽霊との対決。
といっても、アメリカ公使オーティス一家の精神には目の前にいる幽霊を信じないという類(たぐい)の非合理もありません。
幽霊をちっとも恐がらず、あくまでも理性的に対応するオーティス一家と幽霊のちぐはぐな関係が滑稽で、思わず笑い転げてしまうドタバタコメディーが展開されます。
そして最後には大感動の結末が用意されています。
ただ滑稽なだけでなく、この結末があるために、このお話は一際光を放って輝きます。
名にし負うオスカー・ワイルドの小説ですから、風刺やら寓意をくみ取って深読みすることもできるのでしょうけれど、そんな七面倒臭い読み方をしなくても大丈夫。
おかしいところは大笑いして、感動的なところは心を打たれ、そのまま素直に楽しんで、それで、充分おもしろく読めるお話です。
ちょっと頑固な愛すべきお爺さんと言った性格の、幽霊のサイモン卿が魅力的。
彼は自分の仕事、つまり幽霊であることにとても律義なのです。
それがまた彼の悲喜劇の原因でもあるのですけれど……。