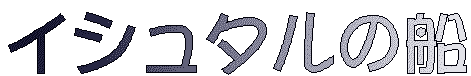
 アメリカの資産家ジョン・ケントン。
アメリカの資産家ジョン・ケントン。
彼は、第一次世界大戦に将校として従軍して以来、
人生に倦み疲れ、長年の考古学への情熱も失って、
虚無の思いにおのれを委ねて生きていた。
そんなある日、彼のもとへ、彼が財政の援助をしている考古学者フォーサイスから、
バビロンで出土したという石盤が送られてくる。
石盤から漂い出てきたかぐわしい香りと不思議な声に導かれ、
ケントンが石盤を割ると、なかには宝石で作られた精巧な古代の船の模型が封じ込められていた。
船の上には実物そっくりの小さな人形すら置かれている。
ケントンが模型の船を見つめるうちに、部屋には銀色の霞(かすみ)が立ちこめて、
それが船を包むと、模型の船は怒涛の大海原に浮かぶ本物の船へと変じ、
ケントンはその甲板に叩きつけられていたのである。
生命を与える愛の神“イシュタル”の第一の巫女(みこ)ザルパニトと、
生命を奪う死の神“ネルガル”の第一の神官アルサルを罰するために、
神々が仕立てた不思議な魔法の船だった ザルパニトとアルサルは、対立する宿敵同士の神に使える身でありながら、
互いに愛し合ってしまったのである。 しかし二人は、神々の妨害にも負けない愛の炎を燃やして結び合い、
自由を得て船を去った。 あとには互いに憎み合うイシュタルの巫女とネルガルの神官が残され、
船は二人がいなまなってなお、神の気まぐれによってか、
あてどももしれぬ航海を続けているのである。
この世界でケントンは、
イシュタルの依代(よりしろ)であるシャラーネに恋をする。
そしてイシュタルにもネルガルにも誓いを立てていない特殊な立場を利用して、
ネルガルの第一の神官クラネスを倒し、
船を自分のものとして彼女をわがものとするために、
熾烈(しれつ)な戦いに身を投じることになったのだ。
船は、
イシュタルを奉じるるものとネルガルを奉じるものの領域にはっきりと分かたれて、
両者が交わることはできないようになっているのだが、
どちらの神にも信仰を捧げていないケントンは、
障壁を越えてどちらの領域をも自由に行き来することができるのだ。
ケントンはこうして、船の上ではたいへん有利な状態におかれているのだが、
これもまた神の気まぐれによるものか、
ときどき思わぬときに現代世界の自分の部屋に戻されてしまう。
そのため、彼が短い時間を過ごす間に、
船では長いときがたってしまうという不都合をも甘受しなければならない。
現代での時間の進み方とイシュタルの船での時間の進み方は必ずしも同調してはいないのだ。
古代バビロニアと、その異界であるイシュタルの船の時間も、同じに流れているというわけではないらしい。
なぜ自分がこういう立場におかれることになったかもわからぬまま、
ケントンはこうして、
古代バビロニア時代の異界と現代を何度も行き来しながら大冒険を繰り広げることになる。
どうやら彼は、叡知(えいち)の神“ナブ”によってこの場に投じられたらしいのだか……。
ケントンにとって、 古代バビロニアでの生活は確かに苛烈で辛い戦いの日々には違いないのですが、
現代のなかで彼が失ってしまった確たる目的を持って、
真の自分をひたむきに生きることのできる、輝くような日々でもありました。
燃えるような愛。
厚い友情。
そして、強い男であることの快感……。
幻想的な筆致で作者が丁寧に描いて見せる古代バビロニアの世界は、
非常に暗いハードなイメージですが、そのゆえにいっそう、
この世界では愛も友情も際立って輝きます。
最下層の奴隷の境遇から身を起こし、
王者となって女の愛を戦い取るというストーリーは、
基本的に男の夢の世界なのかもしれません。
ケントン発想は、
決してシャラーネと対等の立場で彼女と愛し合おうというものではなく、
彼女の支配者となって彼女を従わせようというものなのです。
そしてシャラーネもまた、ケントンの思惑通り、
船を制した彼に、あっけないほど簡単に身も心も捧げてしまいます。
長年の彼女の夢──、
ネルガルを奉じる者たちに勝利するという願いをかなえてくれたケントンに彼女が心を奪われるというのもわかるのですが、
“いするぎ”としては、あまりに単純すぎて彼女の心理にはちょっと乗れません。
まあ、この小説、感情移入の対象になるのは、
あくまでシャラーネではなくケントンなので、
あんまり気にしないで読んでしまえばいいのでしょうけれど……。
女性の登場人物では、ベルの神官シャラムゥーに恋をしてかなえられず、
相手も、そして自分自身をも滅ぼしてしまう絶世の美女、
ベル神の舞姫レディ・ナラダが、 この物語の女としては珍しく、
自分を押し通すたいへん強い意志の持ち主として印象的です。
どちらかと言えば類型的な女たちと比べて、
ケントンと友情を結ぶ男たちは個性的に描き分けられて、
それぞれ独特の魅力を放っています。
クラネスに捕えられて船を漕ぐ奴隷とされてしまったケントンを助け、
かの世界での彼の最初の友人となる勇猛果敢なバイキンクのシグルト。
熱病によって美しい髪をなくしてしまったことがすべての災難の種であるとして嘆く、
ネルガルの神官ギギ。
同じくネルガルの神官であるペルシア人ズブラン。
彼らは、ケントンが語って聞かせるケントンの世界、
つまり、自分たちの未来の世界を知って、
口々にそういう世界にはとても住めない、居場所がないと、
私たちの現代世界を否定します。
それがつまり、そのままケントンの、そして作者自身の思いなのでしょう。
こちらの世界ではわずか九時間という短い時間の間に、
みずからの本当の人生をすべて生き尽くしてしまった男の物語です。
異界への憧れ、息もつかせぬ冒険譚にしばしの夢を結んで、
物悲しい余韻のある読後感が残ります。