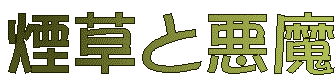
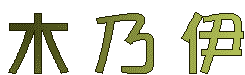
天文年間、天主教──キリスト教──の伴天連(ばてれん)──神父──が日本へ布教にやって来たとき、彼には悪魔が一人ついて来た。
ところが困ったことに、布教が始まったばかりの日本では、まだその信者もおらず、したがって悪魔が堕落させるべき相手もいなかったのである。
日本の寺ののどかな鐘の音を聞いていると、心もゆるんで、悪を行おうという気力も薄れてきてしまう。
退屈を紛らわせるために、悪魔は畑を作って園芸を始めることにした。
やがて悪魔の撒いた種は大きくなり花をつけたが、悪魔は誰にもその花の名前を教えない。
そして悪魔は、新たに天主教の信者になった牛商人を相手に、この花の名前を当てたら畑のものをみんなやるかわりに、当たらなかったらその魂をもらうという条件で賭けをするのだが……。
ペルシャ人の武将パリスカス。
彼は、ペルシャ王カンビュセスがその軍を率いてエジプトに侵攻したとき、これに従って生まれて初めてエジプトの地に入った。
ところが彼は、それまでエジプト人と接したことなどまったくないにもかかわらず、彼らの言葉が理解できることを知る。
その上彼は、初めて見るエジプトの文字を読むことさえできたのだ。
もともと、沈鬱で皆となじまぬ変わり者であったパリスカスは、こうしてエジプトの風物を目にするうちに、その沈鬱な興奮をさらに強くして、狂気の相を強くしていった。
そして、カンピュセス王が、エジプトの先王アメシスの墓所を暴こうとしたとき、アメシス王の墓を捜すための墓所捜索隊に加わって墓の一つを暴いたパリスカスが知った恐ろしい事実とは……。
 国語の授業というのは、本を読むのが嫌いな人間を大量生産することを目的にしているのではないかと、私は邪推しています。
国語の授業というのは、本を読むのが嫌いな人間を大量生産することを目的にしているのではないかと、私は邪推しています。
文章を細切れにして、いじくりまわし、分析し、無理やり結論を出してしまう……。
国語の教科書で扱う教材としての小説の主題は道徳的なものに限られ、そこからは教訓が引き出され、本を読むということは、すなわち、お説教を聞くのと同じことだという先入観を植えつけようとします。
さらに、国語の授業では、本来各自の個性や状況次第でさまざまに感じられる感想はねじ曲げられ、教師の思う方向に統一されてしまいます。
本を読んで書かせる読書感想文。
あれも本の嫌いな人間を作る大きな原因の一つでしょう。
だいたい、感想文を書くために義務で読書をするなんておもしろくないではありませんか。
ああした国語の授業で、徹底的につまらないものに分解されてしまった作家や作品というのも不幸なものです。
授業で習った作家の小説なんぞ二度と読む気がしないというのがおおかたの人の思いでしょう。
で、教科書の定版作家、芥川龍之介と、中島敦です。
その作品を教科書以外のところで知ることができていたなら、もっとずっとおもしろく読めたはずだと、もったいなくてならない作家たちです。
教科書で習った「杜子春」だって、「蜘蛛の糸」だって、無心に読めば、たいへんおもしろいファンタジーの作品です。
ちなみに、「蜘蛛の糸」を読んだ私の正直な感想は、カンダタ(字がない!!)や地獄の亡者たちがかわいそう、お釈迦様は大嫌い、というものです。
地獄の責め苦を何とか脱したいと、そのために死に物狂いになってしまったカンダタよりも、ちょっとした気紛れで、地獄の苦しみに喘ぐ人間に一縷(いちる)の望みを与え、それをいとも簡単に断ち切ってしまって、気怠(けだる)い極楽の午後のなかに何事もなかったように歩み去っていくお釈迦様のほうが、私には忌むべき相手に思えてしまうのです。
他にも芥川龍之介には、「酒虫」、「仙人」、「女仙」、「犬と笛」などといったファンタジーの作品があるのですが、そのなかから、
「煙草と悪魔」という小品を紹介してみました。
たぶんこれは教科書に取り上げられることはないでしょう……、ないんじゃないかと思うんですが……。
のんびりしていてユーモアに溢れた悪魔が、何となくかわいくて気に入っています。
中島敦は「山月記」がたぶん教科書の定版でしょう。
これはもうお馴染みの、人から虎への変身譚で、もちろん立派なファンタジーです。
比喩的な意味をも含めて、どちらかと言えば、虎になってしまいたいなと思う私なのでありました。
中島敦にも、他にやはりいくつものファンタジー作品があって、冒頭で紹介した
「木乃伊」や、それから「文字禍」なんかがお薦めです。
深い意味を含んではいるのですが、この著者の作品のなかでは、軽くて肩の凝らないお話です。
もっともこれらは舞台が日本ではありませんから、本当は“変形する過去〈外国編〉”に分類するべきお話です。
「木乃伊」は、自分がエジプト人の生まれ変わりであることを知ったペルシャ人パリスカスが、前世の自分のミイラと対面して、さらに恐ろしい真実を知る話。
「文字禍」は、王様から文字の霊について研究するよう命じられたアッシリヤの老博士ナブ・アヘ・エリバ氏が、文字の霊が人間を食いつくし、蝕んでいくことを発見するお話です。
国語の授業の悪夢を離れて、無心に一度、こういう作家の作品を楽しんでみるのも一興かと思うのですが、いかがなものでしょう。